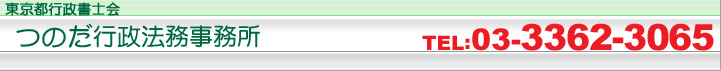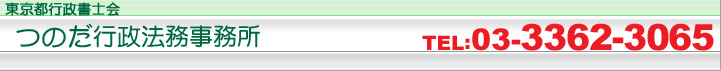|
|
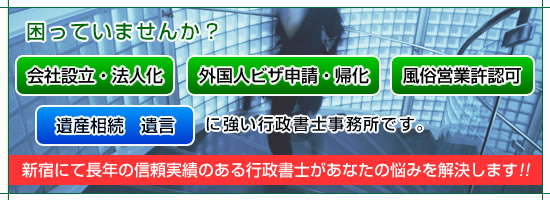 |
 |
 |

|

| |
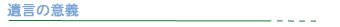
誰が誰の相続人となり、またその相続分はどれほどなのか? といったようなことは、民法によって細かく定められており(これを法定相続といいます)、法定相続は被相続人(相続される者)の死亡によって
当然に開始されます。しかし、この法定相続は、法によって画一的に定められているため、すべての家庭の事情に則して妥当な結果を導けるとは、必ずしも限りません。 一方、遺言は、こうした法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、相続財産に関する権利関係の帰属を、
遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。このように、遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言制度の存在する意義があるといえます。むしろ、相続は遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないともいえるでしょう。
ところで、法的に効力のある遺言をするとなると、その方式及び内容は法に適合したものである必要があります。遺言は、遺言者の生前の意思をその死後において実現させるものであり、それもとりわけ財産に関するものが中心なため、遺言の存在や内容の真実性が保証されなければ争いが生じてしまいます。このような争いを防ぐため、民法は遺言の要件を厳格に定めているのです。 |
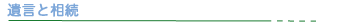
遺言と相続には密接な関係があります。有意義な遺言をするには、相続の基礎知識を知る必要があるでしょう。さっそくですが、右の相続関係図を見て下さい。これは相続される人(被相続人☆)が亡くなり、配偶者(1)と、その子が2人(2、3)残されたといった事例です。この場合、特に遺言がなければ、配偶者と子が法律上当然に相続人となります。
各自の相続分も法律で決められており、この場合配偶者が4分の2、子がそれぞれ4分の1づつを相続することになります。しかし、被相続人が遺言をすれば、この原則を変えることが可能なのです。
|
図
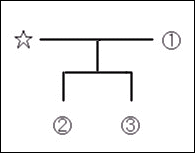 |
| 例えば、子が悪さばかりして遊びほうけているから、財産は全部妻に譲り、子には何もやらないといったことを遺言することも可能なのです。この他にも、単なる知り合いへの遺産の贈与や、社会福祉団体などへの寄付など、どのような遺言をするかは遺言者自身の自由なのです。ただし、この場合でも遺留分といった制度の範囲で遺言は制限されることになります。このように、法律で定められた相続関係は、遺言によって変更することができ、その一方、遺留分などといったもので遺言も一定の範囲で制限を受けることになるのです。
|
|
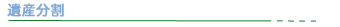
遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きをいいます。相続が開始されると、共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、遺産分割が行われるまでその財産を共有することになります。そしてこの共有となった財産は、遺産分割によって個別具体的に各相続人に分配されることとなるのです。
相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いていつでも遺産分割の協議をすることができます。財産ごとに相続人をきめたり、財産を売却して得た代金を分割したり、様々な分割の方法が考えられます。共有とされた相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されることとなりますが、遺言で相続分や遺産分割の方法が指定されることもあり、また遺言で委託された第三者が分割方法を指定することもあります。ただし、この場合でも、相続人全員の合意によって、法定相続分や遺言または委託された第三者の指定とは異なる分割をすることができます。
なお、共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、最終的に相続人の請求によって家庭裁判所が分割を行うことになります。(民法906条・907条)
|
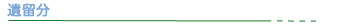
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことをいいます。遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。
遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます(減殺請求=「げんさいせいきゅう」といいます)。ただし、この減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなります。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することもできません。なおこの場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)代襲者が遺留分を主張することができます。
遺留分の割合は以下の通りです。 |

| 1 |
直系尊属のみが相続人である場合
は 遺産の3分の1 |
| 2 |
その他の場合 は 遺産の2分の1 |
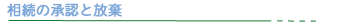
相続によって相続人に帰属することとなるのは土地や預貯金といった財産(積極財産)だけではなく、被相続人が生前負っていた債務など(消極財産)もすべて承継することになります。被相続人が多額の借金を負っており、財産が何もないといったような場合、それを常に相続人が引き継がなければならないとすれば、大変酷な話です。そのため、法は、相続人が自分の意思によって相続するか(承認)否か(放棄)を決めることができるとしました。
この相続の承認・放棄は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月の考慮期間内にしなければなりません。単純承認(後述)の場合には、単にその旨の意思表示をすることで足りますが、限定承認(後述)・放棄の場合は一定の方式のもと、家庭裁判所に対する申述をしてしなければなりません。なお、この相続の承認・放棄は、詐欺・脅迫によってした場合などを除き、原則として取消すことはできません。
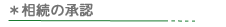
相続の承認には、『
単純承認 』と『 限定承認 』といったものの二通りがあります。 『
単純承認 』とは、被相続人の財産の他、権利関係すべてをそのまま承継するものです。前述した通り、単にその旨の意思表示をすれば足ります。なお、積極的に単純承認をしない場合でも、次のような場合には単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認といいます)。ただし、次の要件に該当する場合でも、その相続人が放棄をしたことによって次順位で相続人となった者が相続の承認をした場合には、その次順位の相続人の利益を保護するため、単純承認したとはみなされないことになります。(民法921条)
|

| 1 |
相続財産の全部または一部を処分したとき。
|
| 2 |
前述した3ヶ月の考慮期間内に限定承認または放棄をしなかったとき。
|
| 3 |
限定承認・放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、またはその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき。
|
『 限定承認 』とは、被相続人から相続する債務などを弁済する責任が、相続する財産の範囲に限定されるといったものです。つまり、限定承認をすれば、相続した財産だけでその債務を完済できない場合でも、相続人自身の財産でもってその不足分を支払う必要はなくなるのです。この限定承認は、前述した考慮期間内にその財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません。また、相続人が複数いる場合は、限定承認は相続人全員が共同してする必要があります。(民法923条)
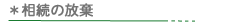
相続の開始後は、3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによって相続の放棄をすることができます。相続の放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、相続の欠格・廃除などでは認められていた代襲相続も、相続放棄の場合には認められません。
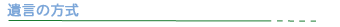
遺言の方式は、『普通方式』と『特別方式』の二つに大別されます。『特別方式』は読んで字の如く特別な事情があって『普通方式』による遺言ができない場合に利用する方式ですので、ここでは『普通方式』を主に解説いたします。
『普通方式』には、『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』 『秘密証書遺言』 の3つがあります。以下にそれぞれの主な特徴と、その比較をまとめてみました。自分の理想にかなう方式を選びましょう。
|
| |
主な特徴 |
自筆証書遺言
(じひつしょうしょ) |
遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることによって作成する方法です。それぞれの要件は非常に厳格で、ワープロで作成したり、日付を年月日までが特定できるように記入しなかったり(例えば「平成13年7月吉日」は不可)した場合には無効なものとなってしまうので注意が必要です。筆記用具や用紙には特に制限はありません。なお、執行のため裁判所の検認が必要となります。(検認については
Q13 参照) |
公正証書遺言
(こうせいしょうしょ) |
遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。適格で完全な遺言書を作成できる代わり、それなりの費用が必要となります。
|
秘密証書遺言
(ひみつしょうしょ) |
遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押した印鑑で封印します。それを公証人1人および証人2人の前に提出して、自己の遺言書である旨および住所・氏名を申述します。さらに公証人がその日付および申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名・押印することによって作成します。遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容に関しての秘密は守られる反面、その内容が不適格であるために結局無効となってしまうといった恐れもあります。なお、執行のため裁判所の検認が必要となります。
|

| 普通方式
|
証人・立会人 |
筆者 |
メリット |
デメリット |
| 自筆証書遺言 |
不要 |
本人 |
遺言を秘密にしておける.費用が少なくて済む |
発見されなかったり変造される恐れがある.方式・内容が不適格な恐れがある |
| 公正証書遺言
|
証人2人以上 |
公証人 |
紛失・変造等を防止できる.適法な遺言が作成できる |
費用がかかる.遺言を秘密にできない |
| 秘密証書遺言 |
公証人1人および証人2人以上 |
誰でもよいが本人が望ましい |
変造等を防止できる.内容の秘密が保てる |
証人等の立会いが必要.内容が不適格な恐れがある |
|
 |
|
|
| Copyright (C) TSUNODA Administration
judicial-affairs office. All Rights Reserved |
|
|
 |